「退職を決意したけど、どうやって上司に切り出せばいいんだろう…」そんな不安を抱えている銀行員の方、多いですよね。
銀行は他の業界と比べて退職の手続きが複雑だし、引き継ぎにも時間がかかります。
でも大丈夫!この記事では、退職の意志を伝える瞬間から最終出勤日まで、すべてのステップを台本・テンプレート付きで完全解説します。
銀行員の転職!まずは全体像——退職までのロードマップ

銀行員の退職は一般企業より時間がかかることを覚悟しておきましょう。金融機関特有の厳格な引き継ぎ要件と、顧客への影響を最小限に抑える配慮が必要だからです。
理想的には2〜3ヶ月、最短でも6〜8週間は見込んでおくことをおすすめします。
いつ誰にどう切り出す?(繁忙期・賞与・案件区切りの見極め)
退職のタイミングは戦略的に選ぶことが重要です。感情的になって「今すぐ辞めたい」と伝えるより、会社にとっても自分にとってもベストなタイミングを選びましょう。
特に銀行は決算期、監査時期、年度末など繁忙期が明確なので、これらの時期は避けるのが賢明です。
退職を切り出すベストタイミング
- 【推奨】4-5月、10-11月(比較的落ち着いた時期)
- 【推奨】大きなプロジェクト完了直後
- 【避ける】3月、9月(決算期・異動時期)
- 【避ける】監査時期、税務調査時期
- 【要検討】賞与支給月(金銭的メリット vs 印象)
必ず直属の上司に最初に伝えてください。同僚や他部署の人に先に話してしまうと、「筋を通さない人」という印象を与えてしまいます。
上司への報告後、人事部門→関係部署→顧客という順序で進めていきます。このルールを守ることで、組織としての信頼関係を保ちながら退職手続きを進められます。
銀行員の退職の切り出し方
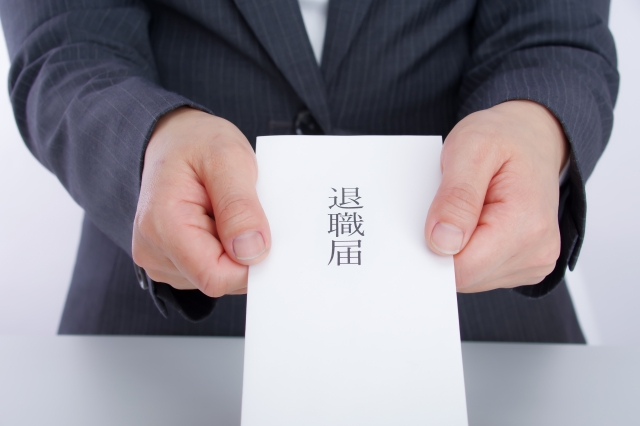
いざ上司に退職を伝えるとなると、緊張で言葉が出てこないこともありますよね。そこで、実際の退職相談まで使える台本をご用意しました。
退職の伝え方(結論→理由→時期→協力依頼)
面談当日は、結論から先に伝えることが重要です。前置きが長いと、上司も何の話か分からず不安になってしまいます。「結論→理由→時期→協力依頼」の順序で、簡潔かつ丁寧に伝えましょう。
面談台本例
「本日はお忙しい中、お時間をいただきありがとうございます。
実は今回ご相談させていただきましたのは、退職についてでございます。
この度、転職することを決意いたしまして、○月末日をもって退職させていただきたく、ご相談に参りました。
理由といたしましては、[具体的な理由]でして、熟慮した結果この決断に至りました。
急なお話で大変申し訳ございませんが、引き継ぎや後任の方への指導等、できる限りのことはさせていただきたいと思っております。
ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします。」
引き止め対応の返し方(条件提示/脅し/情に訴える—ケース別)
退職を伝えると、多くの場合引き止めにあいます。これは決してあなたを困らせるためではなく、貴重な人材を失いたくないという気持ちの表れです。ただし、決意が固い場合は、丁寧かつ毅然とした態度で断ることが重要です。
条件提示への対応
「ありがたいお話ですが、今回は金銭的な条件の問題ではございません。自分のキャリアプランを考えた結果の決断ですので、お気持ちだけありがたく受け取らせていただきます。」
情に訴える引き止めへの対応
「長い間大変お世話になり、本当に感謝しております。だからこそ、中途半端な気持ちでお世話になり続けるより、新しい環境で成長したいという気持ちをご理解いただければと思います。」
脅し・圧力への対応
「ご心配をおかけして申し訳ございません。引き継ぎや手続きについては、規定に従って適切に行わせていただきます。円満に退職させていただけるよう、精一杯努力いたします。」
銀行員の退職理由テンプレ集(使ってOK/避けるNG)

退職理由の伝え方は非常に重要です。本音をすべて話す必要はありませんが、嘘をつくのも良くありません。
前向きで建設的な理由を中心に、相手が納得しやすい形で伝えることがポイントです。ここでは、実際に使える理由のテンプレートと、避けるべきNG例をご紹介します。
前向きな退職理由例(キャリア/適性/家庭)
キャリアアップ系
「新しい分野にチャレンジしたいと考えるようになりました。銀行で培った経験を活かしながら、○○業界でさらなる成長を目指したいと思います。」
「これまでの経験を踏まえ、より専門性を高めたいと考えております。○○の分野で専門的なスキルを身につけることで、将来的により大きな貢献ができると考えています。」
適性・興味系
「自分の適性について改めて考えた結果、○○の分野により強い関心と適性があることに気づきました。この機会にチャレンジしてみたいと思います。」
「学生時代から関心のあった○○の分野で働く機会に恵まれました。年齢的にも今がチャレンジするタイミングだと考えております。」
家庭・ライフスタイル系
「家族の事情により、働き方を見直す必要が生じました。現在の職場には大変感謝しておりますが、家庭との両立を考慮した結果、転職を決意いたしました。」
「地元に戻る必要が生じまして、やむを得ず退職させていただくことになりました。」
退職理由のNG例(待遇不満だけ/他者批判/機密に触れる)
以下のような理由は、たとえ本音であっても避けるべきです。これらの理由は相手に不快感を与えたり、退職後にトラブルの原因になったりする可能性があります。
絶対に避けるべきNG理由
- 「給料が安すぎる」「待遇に不満がある」
- 「上司が嫌い」「同僚と合わない」
- 「仕事がつまらない」「やりがいがない」
- 「将来性がない」「会社に不安を感じる」
- 具体的な機密情報に触れる批判
「本音と建前」のバランスが重要
退職理由は完全な嘘である必要はありませんが、相手を不快にさせない配慮は必要です。
例えば、本音では「給料に不満がある」としても、「より専門性を活かせる環境を求めて」と言い換えることで、同じ意味でも印象が大きく変わります。円満退職のためには、このような配慮が重要です。
銀行退職前後の手続きチェックリスト
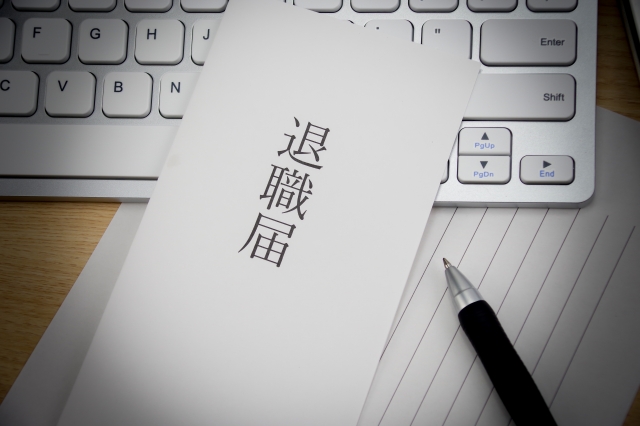
銀行員の退職手続きは一般企業より複雑です。社会保険の手続きから企業年金、持株会まで、様々な手続きが必要になります。
漏れがあると後で面倒なことになるので、チェックリストを作って確実に進めましょう。特に銀行特有の福利厚生制度については、退職のタイミングで大きく条件が変わることもあるので注意が必要です。
社会保険・年金・住民税/源泉徴収票
退職時の社会保険関連手続きは、転職先が決まっているかどうかで大きく変わります。
転職先が決まっている場合は比較的スムーズですが、転職先未定の場合は国民健康保険や国民年金への切り替えが必要になります。
また、住民税の支払い方法も確認しておかないと、後で高額な請求が来て驚くことになりかねません。
社会保険・税務関連の手続きチェックリスト
- □ 健康保険証の返却(退職日当日)
- □ 厚生年金・健康保険の資格喪失手続き(人事部対応)
- □ 雇用保険被保険者証の受け取り
- □ 源泉徴収票の発行依頼(退職後1ヶ月以内)
- □ 住民税の徴収方法確認(一括徴収 or 普通徴収)
- □ 年金手帳の返却(会社保管の場合)
- □ 離職票の受け取り(失業給付申請に必要)
- □ 転職先での社会保険加入手続き
源泉徴収票の重要性
源泉徴収票は転職先での年末調整や、失業給付の手続きで必要になります。退職後1ヶ月以内に発行してもらえるので、受け取ったら大切に保管してください。
住民税の注意点
住民税は前年の所得に対して課税されるため、退職後も支払いが続きます。退職時期によって徴収方法が変わるので、人事部に確認して適切な手続きを取りましょう。
企業年金・持株会・社宅・貸与品返却
銀行特有の福利厚生についても忘れずに手続きしましょう。特に企業年金や持株会は金額が大きくなることもあるので、しっかりと確認することが重要です。
また、社宅に住んでいる場合の退去手続きや、会社から貸与されている物品の返却も計画的に進める必要があります。
企業年金の手続き
多くの銀行では企業年金基金に加入しており、退職時には以下の手続きが必要です:①企業年金基金からの脱退手続き②退職一時金の受け取り手続き③確定拠出年金の移管手続き(iDeCoまたは転職先企業年金へ)④年金資産の運用指図の停止。
これらの手続きには専門的な知識が必要な場合もあるので、人事部や年金基金の担当者にしっかりと確認しましょう。
持株会の清算
従業員持株会に加入している場合は、以下の手続きが必要です:①持株会からの退会手続き②保有株式の売却または個人名義への移管③奨励金・配当金の最終受け取り④口座振替の停止手続き。
株式の売却タイミングによっては税務上の影響もあるので、事前に税理士や人事部に相談することをおすすめします。
社宅退去の注意点:
社宅に住んでいる場合は、退職と同時に退去する必要があります。通常は退職の1-2ヶ月前には退去予定日を人事部に連絡し、原状回復や引っ越しの準備を進めます。
敷金の精算や、修繕費の負担についても事前に確認しておきましょう。転職先が決まっている場合は、入社日との兼ね合いも考慮して退去日を調整することが大切です。
競業避止・守秘義務・データ持ち出し厳禁
銀行員は退職後も様々な義務を負います。特に顧客情報の取り扱いには厳重な注意が必要です。違反すると法的な問題に発展する可能性もあるので、しっかりと理解しておきましょう。
守秘義務について
銀行員の守秘義務は退職後も永続的に続きます。顧客情報、取引内容、内部情報などは一切口外してはいけません。転職活動の面接でも、具体的な顧客名や取引内容は話さないよう注意してください。
競業避止義務
会社によっては、退職後一定期間は競合他社での就業を禁止する「競業避止義務」が設けられている場合があります。就業規則を確認し、転職先が制限に抵触しないか事前にチェックしてください。
よくある質問(FAQ)
銀行員の退職について、よく寄せられる質問をまとめました。退職を検討している方の不安解消に役立てていただければと思います。
- 「就業規則1か月前」と「民法2週間」どっちが優先?
-
法的には民法の「2週間前」が最低ラインですが、円満退職を目指すなら就業規則に従うことを強くおすすめします。多くの銀行では1〜3ヶ月前の申告を求めているので、規則を確認して適切な時期に申し出ましょう。
- 有給休暇を使い切ってから退職したいのですが、可能ですか?
-
基本的には可能です。有給休暇の取得は労働者の権利であり、退職前の消化も認められています。ただし、銀行の場合は引き継ぎや業務の都合もあるため、計画的に進めることが重要です。退職日を決める際に、有給消化期間も含めて逆算し、実際の最終出勤日を設定しましょう。
- 銀行員の転職で最も注意すべきことは何ですか?
-
最も重要なのは「守秘義務の徹底」です。転職活動中も転職後も、銀行で知り得た顧客情報や機密情報を絶対に漏らしてはいけません。面接では「守秘義務により詳細はお話しできませんが」という前置きを必ずつけ、一般化した形で経験を説明してください。次に重要なのは「円満退職」です。金融業界は狭い世界なので、退職時の印象は長く残ります。感情的にならず、最後まで責任を持って業務を遂行し、丁寧な引き継ぎを行うことで、将来的な人間関係やビジネスチャンスを維持できます。
最後に:転職活動も「銀行員としての品格」を保って行うことが重要
在職中の転職活動では、現職への敬意と責任感を最後まで保つことが大切です。転職活動をしているからといって現在の業務を疎かにしたり、同僚や上司への態度が変わったりしてはいけません。
最後まで銀行員としての品格を保ち、プロフェッショナルとして責任を果たすことで、円満な転職が実現できます。また、そうした姿勢は転職先でも必ず評価されるはずです。

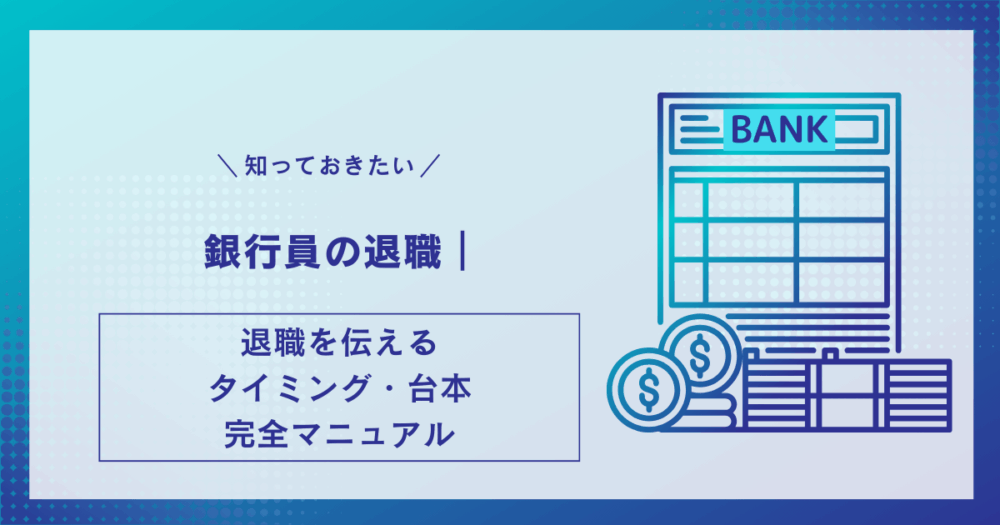


コメント