最近、銀行業界では「銀行 辞める人 多い」というキーワードで検索する人が増えています。
実際、多くの銀行員、特に若手の行員が早期に退職する傾向が強まっています。かつては「安定」の代名詞とされていた銀行業界ですが、今ではその安定性に疑問符が付くようになりました。
この記事では、なぜ銀行員の離職率が高いのか、その背景や理由、そして対策について詳しく解説していきます。
銀行で働いている人、これから銀行員を目指す人、あるいは銀行からの転職を考えている人にとって参考になる情報をお届けします。
銀行員の離職率の現状と背景

皆さんは「銀行員」と聞くと、どんなイメージを持ちますか?
安定した職業、堅実な仕事、それなりの社会的地位…そんなポジティブなイメージがあるかもしれません。
しかし実際には銀行業界は今、大きな変革期を迎えており、多くの銀行員が仕事を辞めていくという現実があります。
特に入社3年以内の若手行員の離職率は驚くほど高く、金融業界全体でも注目される問題となっているんです。
デジタル化の波、低金利政策の長期化、そして顧客ニーズの変化など、銀行を取り巻く環境は厳しさを増しています。この章では、銀行員の離職率の現状とその背景について詳しく見ていきましょう。
若手行員の高い離職率とその実態
「大学を卒業して、やっと憧れの銀行に入ったのに、もう辞めたい…」こんな声が若手行員から多く聞かれるようになりました。
実は、銀行業界における若手行員(入社1〜3年目)の離職率は約25〜30%と言われており、他の業界と比較してもかなり高い数字なんです。
特に都市銀行やメガバンクでは、新卒入社の社員のうち3年以内に退職する割合が年々増加傾向にあります。
- 入社前のイメージと現実のギャップ
- 厳しいノルマや長時間労働によるストレス
- 成長実感やスキルアップの機会の少なさ
- デジタル化に伴う将来性への不安
- 他業界と比較した際の給与水準の相対的低下
この高い離職率の背景には、入社前のイメージと現実とのギャップがあります。
多くの若手行員は「安定した職場」「社会的信用がある」といったイメージで銀行に入社しますが、実際の業務内容や職場環境は想像と大きく異なることが少なくありません。
特に近年は銀行の店舗統廃合やデジタル化による業務変革が進み、従来の「銀行員」のイメージとは違った仕事内容になってきています。
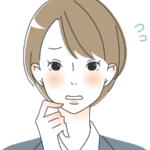
大学の就活の時、「銀行は安定してるから!」って親に言われて入ったけど、実際入ってみたら全然イメージと違った…毎日ノルマに追われて精神的にきついよ…

確かに、銀行のイメージと実態って大きく違うよね。でも、そのギャップをどう埋めるかが大切なんじゃないかな?
また、若手行員の離職理由として多いのが「成長実感の欠如」です。
多くの若手は新しいスキルを身につけたい、自分の価値を高めたいと考えていますが、銀行での業務が単調だったり、専門性を高める機会が少なかったりすることで、成長を感じられないという声も多いです。
さらに、フィンテック企業やIT企業など、新しい金融サービスを提供する企業への転職も増えており、より先進的な環境で働きたいという若手のニーズも高まっています。
金融業界全体の離職率との比較
銀行員の離職率が高いと言っても、それは他の金融業界と比較してどうなのでしょうか?
実は、金融業界全体で見ると、銀行業界の離職率は証券会社や保険会社と比べて必ずしも高いわけではありません。
特に証券会社は景気の波を受けやすく、業績が悪化すると離職率が一気に上がる傾向があります。一方、銀行業界の離職率は比較的安定していますが、近年じわじわと上昇しているのが特徴です。
興味深いのは、銀行の中でも業態によって離職率に差があることです。一般的にメガバンクや都市銀行の方が、地方銀行や信用金庫よりも離職率が高い傾向にあります。
これは、メガバンクでは競争が激しく、ノルマも厳しいことが関係していると言われています。また、都市部では転職市場も活発で、銀行員のスキルを活かせる転職先も多いため、離職のハードルが低いという側面もあるでしょう。
さらに、銀行員の離職率を他業種と比較すると、実はIT業界やコンサルティング業界といった「ハイスキル・高収入」の業界より低いものの、製造業や公務員などの「安定志向」の業界よりは高い傾向にあります。
これは銀行業界が「安定しているが、その分の制約もある」という中間的な位置づけであることを示しています。皆さんが銀行での就職や転職を考える際には、こうした業界特性も理解しておくとよいでしょう。
- 証券会社:約20〜35%(景気により変動大)
- 銀行:約15〜25%(メガバンク・都市銀行は高め)
- 地方銀行・信用金庫:約10〜15%
- 生命保険会社:約15〜20%
- 損害保険会社:約10〜15%

証券会社の離職率がそんなに高いなんて知らなかった!銀行より転職しやすいのかな?

証券会社は成果主義が強いから、景気が良い時は稼げるけど、悪くなると厳しいんだよね。その分、流動性も高いってことだね。
産業構造の変化と銀行員の離職率の関係
興味深いのは、銀行員の離職率が上昇している背景には、単に銀行内部の問題だけでなく、社会全体の産業構造の変化も関係していることです。かつては「一度就職したら定年まで」という価値観が主流でしたが、今では「自分のキャリアは自分で切り開く」という考え方が広がっています。
特に若い世代では、1つの会社に固執せず、スキルや経験を積みながら複数の企業や業界を渡り歩くキャリアパスを選ぶ人も増えています。
こうした社会全体の変化の中で、銀行業界も「終身雇用」から「流動的な人材活用」へとシフトしつつあるのかもしれません。皆さんも自分のキャリアを考える際には、こうした大きな流れも意識してみるといいでしょう。
銀行員が辞める主な理由

「銀行員って、なんで辞めちゃうんだろう?」そう思ったことはありませんか?
安定していそうなイメージの銀行なのに、実は多くの人が辞めていく理由には、様々な要因が複雑に絡み合っています。単に「給料が低い」「残業が多い」といった表面的な理由だけでなく、業界特有の課題や時代の変化に伴う構造的な問題も大きく影響しているんです。
この章では、銀行員が辞める主な理由を詳しく掘り下げていきます。もしあなたが銀行で働いていて「辞めたい」と感じているなら、自分の気持ちを整理するヒントになるかもしれません。
また、これから銀行への就職を考えている人にとっては、入社前に知っておくべき重要な情報となるでしょう。
厳しいノルマとプレッシャー
銀行員が辞める最も大きな理由の一つが、「厳しいノルマとそれに伴うプレッシャー」です。特に営業部門では、投資信託や保険商品の販売、住宅ローンの獲得などに関して具体的な数値目標が設定されることが一般的です。
例えば、「今月は投資信託を○○円分販売する」「個人向けローンを○件獲得する」といった具体的なノルマが課せられます。
このノルマは個人だけでなく、支店全体にも設定されているため、支店長から各行員へのプレッシャーも相当なものになります。
特に近年は、マイナス金利政策の影響で銀行の収益構造が変化し、従来の預金・貸出業務だけでは十分な利益を上げにくくなっています。
そのため、投資商品や保険商品の販売ノルマがさらに厳しくなっている傾向があります。これらの商品は顧客にとってリスクを伴うものも多く、「本当に顧客のためになるのか」という倫理的なジレンマを感じながら販売活動を行わなければならないケースも少なくありません。
こうした状況は、特に顧客第一の姿勢を大切にしたいと考える行員にとって大きなストレスとなります。「ノルマを達成するために無理な販売をしてしまった」「顧客の本当のニーズに応えられていない」という後ろめたさや罪悪感を抱えながら働き続けることは、精神的にとても負担が大きいのです。
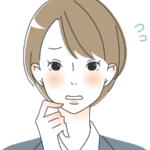
先月、投信のノルマが達成できなくて、上司から「努力が足りない」って言われちゃった…でも、無理に勧めるのも申し訳ないしなぁ…

それ、すごくわかる!顧客のためを思うと積極的に勧められないこともあるよね。でも、ノルマは達成しないといけないし…本当に難しい問題だよ。
- 月末のノルマ達成のためのプレッシャー
- 顧客ニーズとノルマの間での葛藤
- ノルマ未達による評価への影響への不安
- 過度な販売目標による身体的・精神的疲労
- ノルマ達成のための休日出勤や残業の増加
古い企業文化と変わらない風土
銀行業界の「古い企業文化と変わらない風土」も、多くの行員、特に若手行員が離職を考える大きな理由となっています。銀行はその性質上、安定性や信頼性を重視するため、保守的な体質になりがちです。
その結果、「前例踏襲」「慎重さの重視」「階層的な組織構造」といった特徴が強く現れることになります。これらの特徴は銀行の安定性を支える一方で、時代の変化への対応を遅らせ、新しいアイデアや革新的な取り組みを阻害する要因にもなっています。
特に若い世代にとって、「なぜそうするのか」という理由が明確でない慣習や儀礼的な業務が多いことは大きなストレスになります。
例えば、「上司が帰るまで帰れない」「年功序列の強い評価制度」「形式的な会議や報告書の多さ」などは、効率性や合理性を重視する若い世代には受け入れがたい文化と感じられることが多いです。
また、銀行は顧客からの信頼を得るために「誠実さ」「正確さ」「堅実さ」を重視する傾向があります。これらの価値観自体は素晴らしいものですが、それが行き過ぎると「リスクを取らない」「変化を嫌う」「前例のないことはしない」という文化につながりがちです。
デジタル技術の急速な発展や顧客ニーズの多様化が進む現代において、このような文化は時代に取り残されるリスクを孕んでいます。
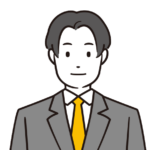
新しいアイデアを提案したら、「前例がない」って却下されちゃった…でも顧客目線だと絶対に喜ばれると思うんだけどなぁ…

わかるよ〜!銀行って「今までうまくいってたから」っていう理由で変化を避けがちだよね。でも、世の中はどんどん変わってるのに…
- 厳格な服装規定(スーツの色や髪型の制限など)
- 年功序列主義による若手意見の軽視
- 形式的な稟議制度や多層的な決裁プロセス
- リモートワークなど柔軟な働き方への消極的姿勢
- デジタル化への対応の遅れ
評価制度やキャリアアップへの不満
銀行員が感じる不満の中でも特に大きいのが、「評価制度やキャリアアップへの不満」です。多くの銀行では、まだ年功序列的な要素が残っており、若くして実力を発揮しても、それに見合った評価やポジションを得るのが難しいケースが少なくありません。
特に、銀行の人事異動は「ジョブローテーション」と呼ばれる制度に基づいていることが多く、2〜3年ごとに異なる部署や業務に移ることが一般的です。
このシステムは幅広い経験を積める利点がある一方で、特定の分野での専門性を高めたいと考える行員にとっては、キャリア形成の障壁となることもあります。
また、銀行のキャリアパスは比較的固定的で、「支店長」「本部の部長」といった伝統的なルートが主流です。
しかし、現代の若手行員の中には、「データサイエンティスト」「デジタルマーケティング」「フィンテック戦略」など、より専門的で新しい分野でのキャリアを望む声も増えています。銀行がこうした多様なキャリア志向に対応しきれていないことも、離職の原因となっています。
さらに、評価基準が不透明だと感じる行員も少なくありません。「何をどれだけ達成すれば、どのような評価を得られるのか」が明確でないと、モチベーションの維持が難しくなります。特に、営業実績だけでなく、顧客満足度や業務改善への貢献など、多面的な評価を求める声も高まっています。
- 実力よりも年功が重視される評価制度
- ジョブローテーションによる専門性構築の難しさ
- 新しい職種やキャリアパスの選択肢の少なさ
- 評価基準や昇進条件の不透明さ
- 自己啓発やスキルアップへの支援不足
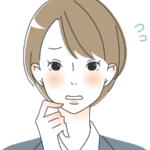
入社5年目だけど、まだ「若手」扱いで重要な仕事を任せてもらえないんだよね。前職ではもっと責任ある立場だったのに…

それ、すごくもどかしいよね。銀行って「若いうちは下積み」っていう考え方がまだ強いから。でも、それで優秀な人材が流出してるってことに気づいてほしいよね…
労働条件やワークライフバランスの問題
銀行員が辞める大きな理由の一つに、「労働条件やワークライフバランスの問題」があります。銀行は一般的に「残業が多い」「休みが取りにくい」というイメージがありますが、実際のところはどうでしょうか?
確かに銀行業務は締め日や期末など、繁忙期には長時間労働になりがちです。特に月末や四半期末には残業が増え、プライベートの時間が削られることも少なくありません。また、支店によっては人手不足から慢性的な長時間労働が発生しているケースもあります。
さらに、銀行の労働環境における特徴的な問題として「サービス残業」の存在も指摘されています。例えば、営業ノルマ達成のために公式な勤務時間外に活動したり、早朝に出社して準備をしたりすることが、「自主的な活動」として扱われることもあります。こうした見えない労働時間が、実際の負担を大きくしているのです。
また、デジタル化が進む中でも、銀行業務には依然として紙の書類や印鑑が必要な処理が多く残っており、これが業務効率化の妨げとなっています。
例えば、顧客からの申込書や契約書類など、電子化されていない書類処理に多くの時間を費やすことになります。こうした非効率な業務プロセスが、労働時間の長さにつながっているケースも少なくありません。

月末になると毎日23時過ぎまで残業…家族との時間がほとんど取れないよ。これって本当に仕方ないことなのかな?

それってキツいね。仕事は大事だけど、家族との時間も同じくらい大切だよね。銀行の働き方も少しずつ変わってきてるけど、まだまだ改善の余地はありそう…
- 月末・四半期末の集中的な業務負荷
- 営業ノルマ達成のための時間外活動
- 紙ベースの手続きによる非効率な業務プロセス
- 人員削減による一人当たりの業務量増加
- 緊急対応や顧客からの急な要望への対応
ワークライフバランス改善への取り組み
こうした状況を改善するため、多くの銀行では働き方改革に取り組み始めています。例えば、フレックスタイム制の導入、テレワークの推進、ノー残業デーの設定、業務プロセスのデジタル化などが進められています。
また、一部の銀行では「勤務間インターバル制度」(前日の終業時刻から翌日の始業時刻までに一定時間の休息を確保する制度)を導入するなど、従業員の健康管理にも配慮した取り組みが見られます。
こうした改革が進めば、銀行員の労働環境も徐々に改善されていくかもしれません。皆さんも、自分のワークライフバランスを大切にし、必要に応じて上司や人事部門に改善提案をしてみることも大切です。健全な職場環境づくりには、働く人自身の声が欠かせないのですから。
銀行員の離職による影響と課題

銀行員の離職率が高まっている現状、これは単に個人のキャリア選択の問題だけではありません。銀行という組織全体、そして金融業界、さらには社会全体に様々な影響を及ぼしています。
特に、熟練した人材の流出は、銀行の業務品質やサービスレベルにも直結する問題です。また、「銀行員が辞める」という現象が広く知られるようになると、新卒採用にも影響が出始めています。
かつては「人気業界」だった銀行業界も、今では若者から敬遠される傾向も見られるのです。この章では、銀行員の離職がもたらす様々な影響と課題について考えていきましょう。
これらの問題は、銀行経営者だけでなく、銀行で働く人々、そして銀行サービスを利用する私たち全員にとっても重要な問題なのです。
人材流出が銀行業務に与える影響
銀行からの人材流出、特に中堅社員や熟練行員の離職は、銀行業務に様々な影響を及ぼします。まず最も直接的な影響は「業務知識やノウハウの喪失」です。
銀行業務には、マニュアルだけでは身につけられない暗黙知や経験則が多く存在します。例えば、複雑な融資判断や顧客との長期的な関係構築など、経験を通じて培われるスキルは簡単に代替できません。そうした知識やスキルを持った人材が流出すると、業務の質やスピードに影響が出ることは避けられません。
また、「顧客関係の断絶」も大きな問題です。特に法人営業や富裕層向けのプライベートバンキングなどでは、担当者と顧客の間に長年かけて築かれた信頼関係が重要です。
担当者が退職すると、その信頼関係も一から構築し直す必要があり、場合によっては顧客離れにつながることもあります。
さらに、熟練行員の離職は「若手育成の停滞」も招きます。銀行業務は基本的に先輩から後輩へと知識やスキルが伝承される側面が強いため、中堅層が薄くなると若手の成長が遅れる可能性があります。
特に、複雑な判断を要する業務や顧客対応のノウハウなどは、日々の業務の中で先輩の姿を見て学ぶことが多いのです。

担当していた法人のお客様から「前の担当者はどこに行ったの?あの人とならもっと相談しやすかったのに…」って言われちゃった…

それは辛いね…。顧客との関係って一朝一夕では築けないものだから。でも、君なりの強みを活かして、新しい信頼関係を作っていくしかないよね。
- 経験に基づく業務ノウハウの喪失
- 顧客との信頼関係の断絶
- 若手育成の機会減少
- 残された社員の業務負担増加
- 組織の活力低下やモチベーション低下
離職率の高さが新卒採用に及ぼす影響
銀行業界の高い離職率は、新卒採用にも大きな影響を与えています。かつて「人気業界」として多くの優秀な学生が志望していた銀行業界ですが、近年では就職人気ランキングで順位を下げる傾向が見られます。
特に「銀行員が辞める理由」や「銀行の働き方の実態」などの情報がSNSやインターネットで広く共有されるようになり、就活生の間で銀行のネガティブなイメージが広がっていることも一因です。
また、就職活動において学生が重視する要素も変化しています。現在の就活生は「ワークライフバランス」「自己成長の機会」「社会的意義のある仕事」などを重視する傾向が強まっており、長時間労働や厳しいノルマ、古い企業文化といった銀行のネガティブな側面が、こうした価値観と合わないと判断されるケースが増えています。
さらに、IT企業やスタートアップ企業、外資系企業などが学生に人気を集める中で、銀行の相対的な魅力が低下していることも事実です。
特に「デジタル人材」や「グローバル人材」と呼ばれる、これからの時代に必要とされる人材を獲得する競争は激しくなっており、銀行はそうした人材獲得競争で苦戦しているのが現状です。
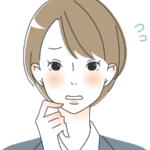
就活生の後輩に「銀行ってどう?」って聞かれて、正直に答えるべきか悩んじゃった…実際の仕事内容とイメージって結構違うし…

それ、難しい問題だよね。でも、良い面も悪い面も包み隠さず伝えることで、ミスマッチを防げるんじゃないかな。入ってから「聞いてた話と違う!」ってなるより良いと思うよ。
- 就職人気ランキングでの順位低下
- SNSなどでの銀行のネガティブ情報の拡散
- 学生の価値観変化(ワークライフバランス重視など)
- IT企業・スタートアップなど他業界との人材獲得競争
- デジタル人材・グローバル人材の確保の難しさ
新卒採用戦略の見直しと職場環境の改善
こうした状況に対応するため、多くの銀行では新卒採用戦略の見直しを進めています。例えば、「デジタル戦略」「グローバル展開」「社会的価値の創出」など、これからの銀行の挑戦や可能性を積極的にアピールする採用活動が増えています。
また、インターンシップの充実や若手行員との交流会など、銀行の実態を知る機会を多く設けることで、入社後のミスマッチを防ぐ取り組みも行われています。
さらに、根本的な解決策として、働き方改革やキャリアパスの多様化など、職場環境そのものの改善を進める銀行も増えています。
こうした取り組みが実を結べば、銀行業界の魅力は再び高まる可能性があります。皆さんも就職活動の際には、表面的なイメージだけでなく、各銀行の具体的な取り組みや職場環境をしっかり調査することが大切ですね。
銀行員としてのキャリアを見直すポイント

「銀行 辞める人 多い」という現状を知った上で、あなた自身はどうすべきでしょうか?
特に今、銀行で働いている方や、これから銀行への就職を考えている方にとって、自分のキャリアをどう考えればよいのかは大きな問題です。
銀行を辞めるべきなのか、それとも残るべきなのか。その判断は一人ひとり異なりますが、客観的に自分のキャリアを見つめ直すことは誰にとっても有益です。
この章では、銀行員としてのキャリアを見直す際に考えるべきポイントや、もし転職を考える場合の注意点などについて解説します。あなたの大切なキャリア選択の参考になれば幸いです。
自分のキャリアビジョンと銀行での将来性の検討
銀行員としてのキャリアを見直す際、最も重要なのは「自分自身のキャリアビジョン」と「銀行での将来性」を照らし合わせることです。まずは自分自身に問いかけてみましょう。
「5年後、10年後にどんな自分になっていたいか?」「どんな仕事をしていたいか?」「どんなスキルを身につけていたいか?」こうした問いに対する答えが、今の銀行での仕事を通じて実現できそうかどうかを考えることが大切です。
また、銀行業界全体の動向や自分が勤める銀行の将来性についても客観的に評価することが重要です。銀行業界は大きな変革期を迎えており、デジタル化やグローバル化、規制緩和などによって従来の銀行業務は大きく変わりつつあります。
こうした変化は「リスク」でもありますが、同時に「チャンス」でもあります。例えば、デジタル戦略部門や国際業務部門など、成長分野での活躍の機会も増えています。
さらに、自分の適性や強みと現在の仕事内容のマッチングも重要なポイントです。「お客様との対話が得意」「数字を分析するのが好き」「新しいことに挑戦するのが楽しい」など、自分の強みや好きなことが活かせる仕事ができているかどうかを考えてみましょう。
もし現在の部署や役割が自分に合っていないと感じるなら、まずは銀行内での異動や配置転換を検討することも一つの選択肢です。
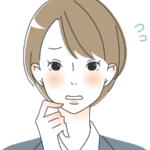
銀行で3年働いたけど、もっとデジタル分野に関わりたいな…でも辞めるべきか、銀行内でのキャリアチェンジを目指すべきか悩んでる…

それは大事な分岐点だね。まずは銀行内にデジタル関連の部署はないか調べてみるといいかも。最近は多くの銀行がデジタル戦略に力を入れてるからチャンスがあるかもしれないよ!
- 自分の価値観・やりがいを感じることは何か
- 今の仕事で身につくスキルの将来性
- 銀行業界・勤務先銀行の今後の展望
- 自分の強み・適性と現在の仕事の相性
- ワークライフバランスに対する自分の優先度
銀行内でのキャリアチェンジの可能性
「銀行を辞める」という選択肢の前に、まずは銀行内でのキャリアチェンジの可能性を探ることも大切です。近年、多くの銀行では組織の多様化や専門部署の新設が進んでおり、従来とは異なる働き方や専門性を追求できる環境が整いつつあります。
例えば、デジタル戦略部門、データ分析部門、市場運用部門、国際業務部門、法人コンサルティング部門などは、特定のスキルや専門性を活かせる場として注目されています。
また、「社内公募制度」や「チャレンジ制度」を活用して、自ら希望する部署や業務にチャレンジする道も開かれています。
さらに、銀行グループ内の関連会社(証券、信託、システム会社など)への出向や転籍という選択肢もあり、グループ内で多様なキャリアパスを描くことも可能です。自分のキャリアビジョンを実現するための道筋を、まずは銀行内で模索してみることをおすすめします。
転職を考える際の注意点と成功のための準備
銀行内でのキャリアチェンジを検討した上で、それでも転職を考える場合には、いくつかの重要な注意点があります。まず、銀行での経験やスキルが他業界でどのように評価されるのかを客観的に理解することが大切です。
銀行員の強みとしては、「数字への強さ」「リスク管理能力」「コミュニケーション能力」「金融知識」などが挙げられますが、一方で「専門的なIT知識」「マーケティングスキル」「創造性」などは、他業界と比べて弱みとなる可能性があります。自分のスキルセットを客観的に分析し、足りないスキルがあれば転職前に補強しておくことが重要です。
また、「なぜ転職するのか」「次の職場で何を実現したいのか」という明確な目的意識を持つことも大切です。単に「銀行を辞めたい」という気持ちだけで転職すると、次の職場でも同じような問題に直面する可能性があります。転職はあくまでも自分のキャリアビジョンを実現するための手段であり、目的ではないことを忘れないようにしましょう。
転職市場においては、銀行員の需要は業界や職種によって大きく異なります。例えば、「フィンテック企業」「コンサルティングファーム」「不動産・建設業界(融資審査経験者)」などでは、銀行での経験を活かせる可能性が高い傾向にあります。
一方で、全く異なる業界に転職する場合は、スキルの転用可能性をよく検討し、必要に応じて資格取得や自己啓発に取り組むことが求められます。
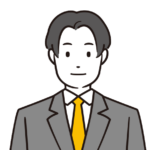
転職したいけど、銀行員って「銀行でしか通用しないスキル」しか持ってないんじゃないかって不安…他の業界でも評価されるものってあるのかな?

そんなことないよ!銀行で培った「数字を読む力」「リスク管理能力」「対人折衝能力」は、多くの業界で重宝されるスキルだよ。自分の経験を適切に言語化することが大切だね。
- 自分のスキルと市場価値の客観的な分析
- 転職の目的と次のキャリアでの目標の明確化
- 不足しているスキルの補強(資格取得・学習)
- 銀行での経験を他業界向けに言語化する練習
- 転職市場の調査と人脈形成
銀行員からの転職成功事例
銀行員からの転職は難しいと思われがちですが、実際には多くの成功事例があります。例えば、法人営業経験を活かして事業会社の財務部門やM&A部門に転職したケース、融資審査の経験を活かして信用調査会社やコンサルティング会社に転職したケース、リテール営業の経験を活かして不動産や保険業界に転職したケースなどが見られます。
また、デジタル化やフィンテックの流れを受けて、IT知識を習得した上でフィンテック企業やIT企業に転職するケースも増えています。成功している転職者に共通するのは、「銀行での経験を具体的な成果とスキルに落とし込み、転職先でどう活かせるかを明確に説明できる」という点です。
単に「銀行で〇年働いていました」ではなく、「どんな課題にどう取り組み、どんな成果を上げたのか」を具体的に伝えられることが重要です。転職を考える際は、まず自分の経験を棚卸しし、具体的なエピソードや数字で語れるように準備しておきましょう。




コメント